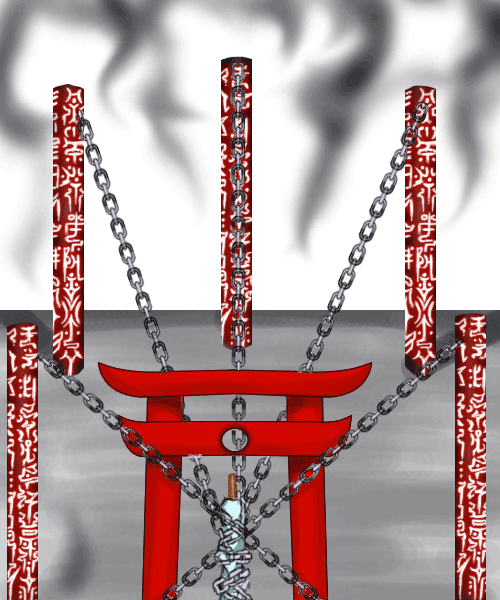
電車を乗り継ぎ更にバスに乗り換え、俺がようやく目的の村に到着したのは夕方近くの事だった。
「距離はたいした事無かったが・・・なんで地方の乗り物はあんなに時間が空くんだ?」
どうも俺は今日タイミングが悪かったらしく行く電車行くバスことごとく発車直後で乗り遅れてそれに時間を大幅に取られる形となってしまった訳である。
「え〜と、目的の神社は・・・まだ距離があるな・・・それでも行きますか・・・」
ぼやきと取れる言葉を呟くと俺は荷物を手に歩き始めた。
虫の音が心地よく聞こえる林の中を俺は歩く。
懐かしさを覚えるのは『七夜の森』での思い出の所為だろう。
日も大分傾いている。
「まいったな・・・このままだと野宿か?」
軽口を叩きながら歩を緩めない。
この村にホテルはもちろん民宿すらないことは承知している。
そうなると本当に野宿を考えないといけない。
やがて目的の神社が見えてきた時だった。
カタ・・・
ナップザックの中から音が聞こえた。
「??」
カタ・・・カタ・・・
音はやはり聞こえる。
「これって・・・」
「どう言う事だ・・・」
俺も鳳明さんも唖然として立ち尽くした。
俺はこの現象を過去に一度耳にしている。
かすかに震える手でそれを取り出す。
震えていたのはやはり『凶断』・『凶薙』の二本。
「なんだ?どうして震えている?」
俺は訳がわからなくなりながらも神社の鳥居をくぐる。
その途端、二本の震えは大きくなる。
「なにかあるな・・・この二本が共鳴を起こすほどの何かが・・・」
とにかく、俺はその震えに誘われる様に神社の裏手に回る。
やがて奇怪なものが見えてきた。
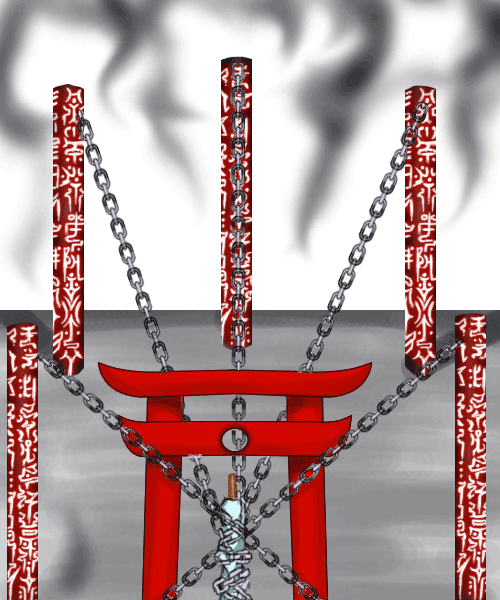
それは、東西南北更に、南東、東北、西南、北西それぞれに奇怪な文字がびっしりと掘り込まれた石柱に囲まれた鳥居らしきものが。
そしてその中には更に奇怪なものがあった。
それは石柱から伸びる八本の鎖にぐるぐる巻きにされた細長い何か。
長さから言って七十・・・いや八十メートルほどあるだろうか?
鎖の合間にはやや変色した布が見える。
どうやら、布で巻きつけて更に鎖を使いここに固定されているようだ。
気が付くと、震えは収まっている。
(どうもここが目的の場所のようですね・・・鳳明さん?)
(・・・志貴・・・なんだ?あれは?・・・)
何時もの鳳明さんらしくない程その声は震えていた。
(どうかしたのですか)
(志貴アレには・・・)
その時だった。
「こらっ!!!!お主ここで何をやっておるか!!!」
後ろから怒鳴り声が聞こえたのは。
「うわっ!!」
後ろに気を取っていなかった俺はまさに跳び上がるほど驚き振り向くと、そこにはいかにも気の強そうな頑固爺さんが立っていた。
服装からいって神社の宮司だろうか?
「むむ・・・服装から言って観光客か?」
胡散臭そうな視線で俺を睨みつける宮司の爺さんに俺は用意した台詞を言った。
「いえ。俺は大学で民俗学を専攻している学生です。ここに面白いお話と史跡があると伺いましたので」
その言葉を聞くと爺さんは一瞬で機嫌を直した。
「ほう、そうか・・・そうか・・・それは遠い所から良く来たのう・・・」
内心でほっとした。
(で、その神社の宮司の爺が偉く頑固者でな、マスコミだの観光客とか言えば、速攻追い出される。ただ純粋に調べに来た学者や学生には結構親切に接するらしいからその手を使いな)
たまには役に立つ事を言う悪友に内心で感謝しながら俺は率直に尋ねる。
「宮司さん、これは何なのでしょうか?」
と、あの社を指差す。
「ああ、これはの・・・まあ、長い話になると思うから家に来なさい」
「えっ?よろしいのですか?」
「ああ、爺一人だからなどうせ宿は無いのであろう?」
「えっ?・・・ええ」
「ならば来なさい。たいしたもてなしは出来ぬが食事と寝床は提供できる」
「よろしいのですか?」
「ああ」
「ありがとうございます。ではお言葉に甘えさせていただきます」
そう言って俺は宮司さんの後について行った。
神社の裏手にあるやや古びた日本家屋に案内された俺は荷物を案内された部屋に置くと早速宮司さんに尋ねた。
「それで早速ですが・・・お話を」
「うむそうじゃな。では・・・話すとしようか・・・」
今から千年以上も前の話じゃ。
その当時この近辺には鬼が住んでおると言われておっての・・・その鬼は毎日の様に村や都に下りては人に襲い掛かったと言う。
鬼は不思議な事に人の肉は食わず人の魂を食らっておった。
その為鬼が去った後にはまるで眠りに付いたかのように死に絶える人が溢れ返っておった。
無論その鬼を退治せんと数多くの武芸者や腕自慢の豪族が鬼に挑んだ。
しかし、その鬼に逆に魂を食われてしまい何時の日か誰も鬼に歯向かおうとする者はいなくなってしもうた。
人々は無論恐怖に怯え、絶望にその身を沈める毎日じゃった。
そして、数年後のある日とあるお武家様がこの地を訪れた。
そのお武家様は鬼の事を聞かれると直ぐに鬼が住むこの山に向かわれた。
人々はもう希望など持っていなかった。
また何時もの日に戻る。
そう誰もが確信を抱きさえして興味が無いように各々の家に戻ろうとしていた。
しかし、人々は信じられない光景を目の当たりにしていた。
お武家様が手に持つ刀は神々しいほど赤き光に包まれ、その刀が振るわれる度に鬼は自らの体を傷付けられていった。
今まで誰一人掠り傷すら付ける事すら出来なかった鬼にじゃ。
人々は驚き、そして最後の希望にすがりついた。
その鬼とお武家様の戦いは三日三晩続いた。
しかし、最後にはお武家様はその鬼を消滅させる事に成功したのじゃった・・・
宮司さんの話の要点だけまとめればこうなる。
しかし、実際には話が次々と脱線し夕食もあって気が付けば話を始めて3時間が経過していた。
「なるほどこの地にはそのような伝説があるのですか・・・しかし、あの社の事が出てきませんが?」
俺は納得しながら食後のお茶を啜っていた。
しかし、その中に一度も例の社が出てこない事にいぶかしんでいると
「まあ、落ち着きなさい。実はなこの話鬼を退治した後からが本題なのじゃよ」
「退治した後から?」
「そうじゃ」
鬼は肉体を失ったが魂だけとなっても災いをもたらそうとした。
そこでお武家様はご自分がお持ちになっていらした刀に鬼の魂を封じ込めたのじゃ。
それからお武家様は八本の柱を何処からか用意なされると、それにくまなくなにやら奇怪な文字を彫り込んだ。
そして、刀をその中心に造った粗末な祠に奉納すると村の神社の宮司・・・つまりわしのご先祖様じゃな・・・に柱に刻み込んだ文字を教え最後にこう言い残しこの地を後にしたと言われる。
"これより十年間、今教えた呪言(じゅごん)を毎日欠かさずこの布と縄に注ぎ込め。そして十年後、その布で『闇神』(やみがみ)を包み、縄で『闇神』を戒めよ。これを十年に一度繰り返されよ。そして八本の柱を百年に一度新たな柱に同じ文字を刻み込み抜き変えよ。それを延々と繰り返されよ。さすれば鬼は未来永劫この地に封印されるであろう"とな・・・
「宮司さん・・・『闇神』と言うのは・・・」
話が本当に終わると俺は尋ねた。
「あの社に奉納・・・いや封印されている刀の名じゃ」
ちらりと闇に包まれた社を見る。
「さて、わしの話はここまでじゃ。参考になったかの?」
「はい、大変参考となりました」
「左様か・・・それならばわしも話した甲斐があったと言うもの。それでどの位ここにはいるつもりじゃ?」
「はい、もう暫くここを調べさせていただこうかと・・・」
「さようか・・・若いのに勉強熱心じゃの・・・それならばここに泊まって行くが良い」
「えっ?ですがそれはさすがに」
「何、気にする事は無いもともと頑固爺が一人いるだけ。気兼ね無く泊まって行け」
「はい、ありがとうございます」
その深夜、宮司さんも寝付いた時、俺は外に出ていた。
「・・・『闇神』か・・・」
「・・・志貴・・・」
鳳明さんが出て来た。
「鳳明さん・・・先程は聞きそびれましたが『闇神』の封印された社を見て怯えていたようですがどうされたのですか?」
「ああ、あれか・・・あの強大な封印に少々驚いただけだ」
「封印に?」
「ああ、あれは半端な封印じゃない」
「どうしてそう言えるのですか?」
「当然だろ?あれは事実上四つの封印で『闇神』を封じている」
「四つ?どう言う事です」
俺の問い掛けに鳳明さんは静かに語りだした。
「まず一つ目が『闇神』本体に撒きついている布、あれには強大な封印の呪法が大量に込められている」
「そう言えば宮司さんもそんな事を言っていましたね」
「ああ、そして二つ目が鎖、あれにも布と同等量の呪法を込めてある。普通ならあの二つで大抵の怨霊は身動きすら出来ぬ」
「二つだけでも・・・」
「ああ、そして三つ目にあの八本の柱、あれには一本一本に二つの呪法を施してある」
「二つ?」
「一つが、鎖と布と同じ封印の呪法、それが八本で取り囲み封印の結界を形成している、そしてもう一つは周囲の霊気を集めてそれを結界の力とする呪法・・・」
「鳳明さん、一つ目はわかりますが二つ目と言うのは・・・」
「そこで四つ目が出てくる。四つ目はこの地そのものだ」
「地?」
「この地は地形上の関係かわからんが、霊気が集まりやすい、それを吸収して結界は無限に形成される。この封印をされている以上『闇神』に何が封じられていようとも出る事は到底叶わぬ・・・しかしだ・・・しかし・・・最も恐ろしい事にそれだけの封印にもかかわらず『闇神』の中の何かは未だに強大な力を誇っていると言う事だ・・・あれだけの結界・封印を施されながらだ・・・普通の魂魄なら百年単位で消滅すると言うのに・・・」
「・・・・・・じゃあ鳳明さんでも?」
「当然だ。俺でもあの結界に入ってあれだけの長い時間耐えられる保障は出来ん」
「じゃあ、あの封印も」
「けっして大げさではない。あれの封印が解かれた時には何が出てくるのか?どう言った災いが降り注ぐか?・・・俺にもわからん」
その言葉を最後に俺達は暫し無言となる。
「そういえば・・・最初『凶断』・『凶薙』が共鳴を発しましたがそれはやはり・・・」
「間違いなくこの『闇神』だろうな・・・そうなるとこれが『至高の一刀』なのか?」
「わかりません・・・しかし、ここをもう少し詳しく調べないといけませんね・・・」
「ああ・・・この地にはまだなにかある・・・俺の推測だがな・・・」
その会話を最後に俺達はただ無言で封印を続ける『闇神』を見続けていた。